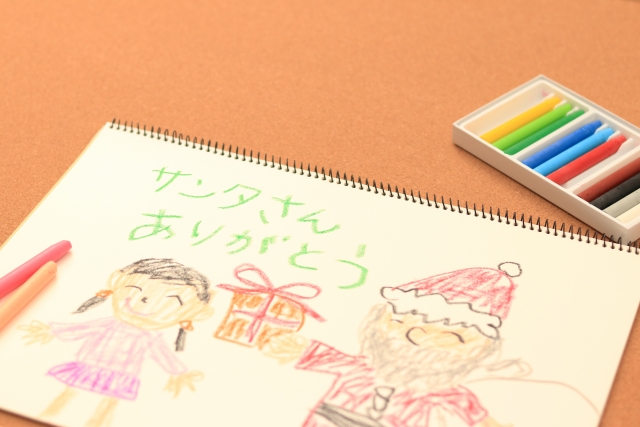世の中の全ての事象に関して言えることかもしれませんが、これくらいが丁度いい、あるいは心地良い、といった「度合い」ってありますよね。程良いバランスとも言い換えられるでしょうか。
要するに、似顔絵で言えば、どの程度まで似ていればいいのか、どこまでリアルに描けばいいのか、逆に言うと、どこまで崩していいのか、どれくらいデフォルメしたらいいのか、といった「度合い」です。
これは、受け取る人によってもその尺度が違ったりするので多少やっかいではありますし、TPO等によっても変わってくるものかもしれませんが、似顔絵として一番おもしろい、一番みんなを喜ばせることが出来る「度合い」といったものを、いろいろと模索するのも似顔絵の楽しみの一つだったりします。
また、そういった「度合い」との兼ね合いから、自分の似顔絵のスタイルやタッチ、要するに芸風や持ち味といったものを決めるのも、面白いかもしれません。この辺りは、経験を重ねていくうちに少しずつ掴んでいけるものなんですよね。
そんなことを考えていたら、こんな話を思い出しました。
とある家庭用ゲーム機でのスポーツゲーム。通常のコントローラーではなく、モーションセンサーによる直感的な体感コントローラーを実現していることで大きな話題となり、野球であればボールを投げる・打つ、テニスであればラケットを振るなど、実際にゲーム機を前にそういう動きをすることで、そのスポーツをプレイしている感覚がリアルに得られるというもの。
大勢が集まり、その中の一つである「ボーリング」に興じていた時のこと。やれストライクだ、やれスペアだガーターだと大いに盛り上がっている中、一人がおもむろに、こうつぶやいたのです。
「ねーこれ、実際にそこでボーリングしたほうが早くね?」
たまたま近所にボーリング場があったが故の何気ない発言ではあったのですが、その後、その場にいる全員が、大いに考えさせられたものです。
つまり、皮肉なことに、ゲームとしてリアルになればなるほど、逆にそれがゲームであるということの意味を問われてしまうという現実。
リアルに近付けば近付くほど、じゃあもう、ゲームじゃなくて実際に「それ自体」をやればいいじゃん、となってしまう現実・・・。
まぁ、「それ自体」がすぐに出来ないから、ゲームで仮想体験をする、という意味では、いいのかもしれませんが・・・。
今や、日々テクノロジーも進化していますので、こういう問題は今後もついてまわることでしょう。
同じことは、アニメや映画などでも言えると思います。これも大いに話題となった、フルCG(コンピュータ・グラフィックス)によるSF映画がありました。実写と見紛うほどの動き、髪の毛一つ一つの動きに至るまでのリアルさなど、その出来栄えは大変素晴らしいものではありましたが、そこまでこだわってCGにする意味が分からないといった声が聞かれたのも事実です。
何と言いますか、あまりにリアルすぎて、CGであることのメリット、逆に言えば実写でないことのメリットが、どこにあるのか分からなくなってしまうとでも言いますか・・・。だったら別に、普通に実写でいいよね、っていう。
これも、役者を使うよりも低コストで済むとか、修正や変更がすぐできるから柔軟性が高いとか、実はもちろんさまざまなメリットはあるのかもしれませんが、なんだかそれだけの理由でCGにするというのも、ちょっと考えてしまいますよね。
そういった考え方の正否はともかく、要するに現実に近づける、リアルに表現するということは、皮肉にも、その存在自体の意義を問われるほどに、それなりのリスクを伴うということでもある訳ですね。
さぁ・・・。あなたはどのレベルの似顔絵を目指しますか。